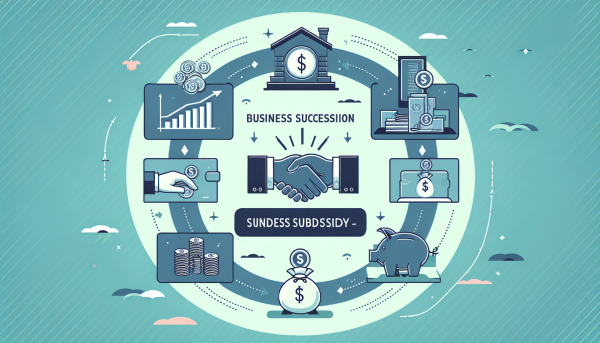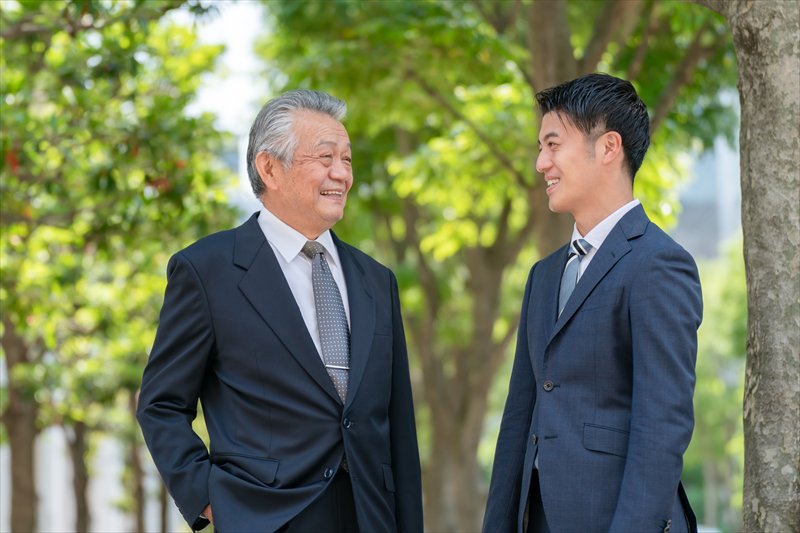
日本の産業を担う中小企業では、少子高齢化や若者の都会流出などが原因で、後継者問題が深刻化しています。
後継者がいない企業は廃業を選ぶしかないのか、後継者問題に直面している中小企業の代表者様は不安を感じていることでしょう。
そこで今回は、中小企業の後継者問題の原因や現状をデータや資料をもとにご紹介し、解決策まで徹底解説していきます。後継者問題にお悩みの代表者様は、ぜひ本記事を問題解決の糸口にしてください。
後継者問題とは?—中小企業が直面する経営の課題
日本の中小企業では、後継者不在による事業の廃業が問題視されています。
廃業する企業の中には、黒字経営が続いている企業や世襲企業も多くあるため、後継者問題を解決しなければ、日本から優良企業や長年培われてきた技術が消滅しかねません。
しかし、後継者問題は単純に担い手となるお子様がいらっしゃらないだけではありません。担い手となるお子様がいらっしゃる場合でも、お子様の経営能力、または相続税・贈与税の観点から簡単に事業を継がせられない状況に陥っている点も問題の一因です。
後継者問題の現状
後継者問題の現状を、具体的な資料やデータと共に見てみましょう。
日本の中小企業における後継者不足の実態
帝国データバンクが公開しているレポートによると、全国の中小企業の後継者不在率は52.1%でした。後継者不在率は年々改善傾向にあるものの、未だ半数以上の中小企業が後継者不足に悩んでいる現状がわかります。
業種ごとの後継者不足の現状と課題
同じく、帝国データバンクが公開しているレポートによると、2024年の調査時点では、建設業が59.3%と最も後継者不在率の高い業種でした。
また、自転車や自動車の小売業、医療業、大工や板金などの識別工事業も、後継者不足率が高い業種です。
これらの業種は、ほかの業種より技術や知識の承継に手間や時間がかかるため、後継者が見つかりにくい傾向にあります。しかし、上記の業種が衰退してしまうと私たちの生活に大きな影響を及ぼしてしまうため、後継者問題の早期解決が求められます。
ちなみに、最も後継者不在率が低い業種は43.8%の製造業でした。
製造業も2018年代は59%と高水準でしたが、製造業の衰退は日本の供給網に大打撃を与えると問題視され、「事業承継・引継ぎ補助金」などの支援が開始された結果、改善されつつあります。
後継者問題が発生する主な原因
後継者問題が発生する主な原因には、以下のものが挙げられます。
1つずつ解説していきましょう。
少子高齢化による後継者候補の減少
日本の人口減少は2011年に始まり、2070年には65歳以上の割合が約40%以上に増加すると予想されています。
2025年現在でも5人に1人が75歳以上というデータが出ているので、そもそも後継者候補になり得る若者がいないのです。
事業の将来性に対する不安
昨今、グローバル化やデジタル技術の進化が急激に進んでいるため、中小企業もこれらに対応する力が求められています。
しかし、グローバル化が進むと競合が世界規模になるため、必然的に今より企業の安定化は難しくなります。また、デジタル技術の進化により、IT技術の活用や事業のオンライン化に対応できなければ、業界で生き残るのは難しいです。
以上の点から、事業の将来性に不安が残る中小企業は、後継者に立候補する人材が現れにくくなっています。
親族内承継の減少
中小企業の多くは、親族内で後継者を選ぶ傾向にあります。
しかし、昨今の少子高齢化問題や、若者の都市部への流出などが原因で、親族内の承継は難しくなりつつあるのが現状です。
中でも、秋田県や鳥取県は親族以外の人物に経営を任せることに抵抗感を抱く企業が多いうえ、都市部へ流出する若年層が多いことから、後継者不在率は70%を超えています。*
事業承継の準備不足
後継者に事業を承継する作業は、後継者の育成機関も含めると最長10年は必要とされています。
しかし、経済産業省の中小企業庁が発表している資料によると、事業承継の準備を終えている中小企業は代表者の年齢問わず、いずれの場合も50%以下でした。
なかでも、代表者年齢が70代~80代の中小企業は、これから準備をするにしても準備期間中に代表者が病気になったり死亡したりして、事業承継が白紙になる可能性が高くなります。
実際に帝国データバンクが公開しているレポートによると、事業承継の計画中止や取りやめを行った中小企業は、全年齢平均2.7%に対し、70代が4.3%、80代が7.0%と高水準です。
以上の点から、事業承継の準備は代表者が50~60代のうちに始めるべきですが、「日々の経営で精一杯」「何から始めたら良いのかわからない」などの理由で、事業承継の準備がスムーズに進みにくい現状があります。
後継者問題の解決策
後継者問題を解決するためには、以下の解決策が有効です。
1つずつ確認していきましょう。
解決策① 事業承継5ヶ年計画の概要を確認して支援を受ける
後継者問題に悩んでいる場合は、まず経済産業省の中小企業庁が策定した「事業承継5ヶ年計画」の概要を確認してみましょう。
事業承継5ヶ年計画には、今後5年間で後継者問題を解決するための支援内容が以下のようにまとめられています。
- 経営者の「気付き」の提供
- 後継者が継ぎたくなるような環境を整備
- 後継者マッチング支援の強化
- 事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備
- 経営人材の活用
具体的には、25万~30万件の中小企業への事業承継診断の実施、事業計作成支援、事業引継ぎ支援センターの強化、サプライチェーンの環境整備、経営スキルの高い人材と企業をマッチングさせる環境つくりが行われています。
後継者問題を早期解決するためにも、各都道府県にある事業承継ネットワークや事業引継ぎ支援センターに相談し、どのような支援を受けられるのか確認してみましょう。
解決策② 親族内承継を進める
代表者にお子様や兄弟・姉妹などがいらっしゃる場合は、中小企業の後継者を決定するメインの手段として用いられてきた、親族内承継を進める方法がおすすめです。
親族であれば信頼関係も確立されていますし、経営方針や今後の展望なども第三者よりスムーズに伝えやすいので、代表者が引退しても事業の安定化を維持できます。
ただし、親族内承継を行うと贈与税や相続税を課せられる可能性が高くなるため、承継前にある程度の資金調達が必要です。
解決策③ 社内の人材を後継者に育成する
親族内承継が難しい場合は、社内の人材を後継者に育成する方法がおすすめです。
社内の人材であれば、経営方針や事業内容が身に付いているので、一から教育するコストを省けます。また、従業員や取引先からも信頼を得やすいので、代表者が引退したあとも経営がスムーズに進みやすいです。
帝国データバンクが公開しているレポートを見ても、2024年は親族内承継を内部承継が上回っています。
昨今では少子高齢化も進んでいるため、今後は親族内承継よりも、社内の人材を後継者に育成するほうが後継者選びの主な手段になるといえるでしょう。
解決策④ 外部から後継者を登用する
親族内承継や内部承継が難しい場合は、外部から経営者スキルを持った人材を登用する方法もあります。
今や中小企業もグローバル化やIT化が求められているので、これらに関する知識や技量を持ち合わせた人材が身近にいない場合は、外部から後継者を採用したほうが事業の成長を期待できる可能性が高いです。
また、外部から後継者を登用すると新しい視点で物事が進むため、自社の弱みも改善されやすく、事業もさらなる進化を遂げやすくなります。
ただし、外部から後継者を登用すると、社風がガラッと変わったり、従業員が新しい経営者に付いてこなかったりといった問題が生まれやすい点が課題です。
解決策⑤ M&Aで第三者に承継させる
自力で後継者を見つけられそうにない場合は、M&Aによって第三者に事業を引き継いでもらう方法もあります。
M&Aで事業承継を行うと、第三者の協力を得てさらに事業を拡大できる可能性が高まります。後継者不足により本来であれば廃業に追い込まれるはずだった企業でも、自社の価値を維持しながら成長できる点は、大きなメリットです。
ただし、承継先の企業を事業の合間に見つけ出すのは難しく、場合によっては第三者への承継で廃業に追い込まれる可能性もあるため、M&Aは専門業者へ依頼をしましょう。
M&Aの専門業者へ依頼をすると、自社の現状や展望に見合った企業を紹介してもらえるうえ、合併の交渉や手続きなども一任できます。プロに依頼をすれば、不要なトラブルに巻き込まれる心配なく事業継承を行えるので、安心です。
解決策⑥ 事業引継ぎ支援センターを活用する
後継者問題に悩んでいるものの、何から始めたら良いのかわからない場合は、事業引継ぎ支援センターを活用してみましょう。
事業引継ぎ支援センターとは、中小企業に対して事業承継支援を行っている公的機関です。各都道府県の商工会議所内に設置されており、無料相談だけでなく、アドバイスやサポート、M&A買手候補の紹介支援を受けられます。
なかでも、M&Aの買手候補情報は、全国の支援センターと情報を共有しているので、条件によっては県外の候補先ともマッチング可能です。
ただし、事業引継ぎ支援センターは買手候補との交渉までサポートしていないので、マッチングを受けたあとは自力で交渉しなければならない点がデメリットといえます。自力での交渉が難しい場合は、法律事務所や投資銀行などの専門機関にサポートを依頼しましょう。
<支援別の専門機関>
| 専門機関名 | 主な支援内容 |
|---|---|
| 投資銀行 | M&Aの交渉支援財務分析契約書作成支援企業価値評価 |
| 法律事務所 | 3億円 |
| 会計事務所 | 財務分析企業価値評価買収監査(デューデリジェンス) |
| コンサルティングファーム | M&A戦略の策定事業承継支援企業再編のアドバイス |
| 企業再生支援機関 | 財務再生・業務再編支援経営改善のアドバイス |
解決策⑦ 廃業する
後継者問題を解決する最終手段は、廃業です。
経済産業省の中小企業庁が発表している資料を見ても、60歳以上の代表者の50%が廃業を選択しています。
廃業の理由は「当初から自分の代でやめようと思っていった」が38.2%と最多で、「子どもがいない」などの後継者難が28.6%、「事業に将来性がない」が27.9%でした。
確かに、廃業を選択すれば後継者問題は解決します。しかし、資料を見ると廃業を選択した企業の約30%が好成績を挙げており、40%の企業が今後10年間の将来性を期待できると回答しているので、後継者問題の解決方法ですぐに廃業を選ぶのはもったいないです。
後継者問題はM&Aで第三者に承継させると、企業のノウハウや従業員の生活、および社会への貢献を守りながら解決できる可能性があります。そのため、後継者問題に悩んだ場合は、廃業を選択する前にM&Aで第三者に承継させる方法を検討してみましょう。
まとめ
少子高齢化による担い手不足、後継者の経営能力低下や相続税・贈与税の支払いなど、さまざまな観点から、日本の中小企業は後継者問題に悩まされています。
なかでも、建設業や自転車・自動車の小売業、医療業、大工や板金などの技術職は、ほかの業種より技術の承継に時間や手間がかかることから、後継者不在率が高いです。
ただし、昨今では経済産業省を中心にさまざまな支援が実施されています。後継者問題の解決策には複数の選択肢があるので、後継者の選定にお悩みの方は、廃業を選択する前に、まずは支援を受けてみましょう。