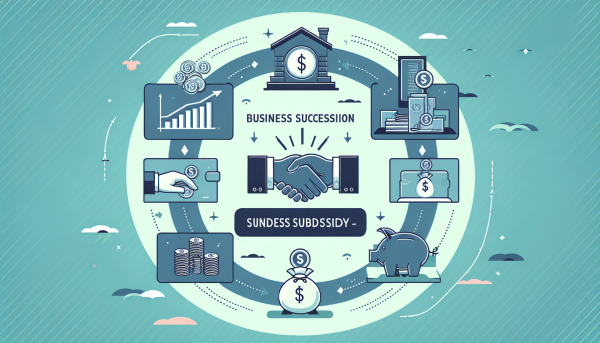事業継続の大きな岐路となる「事業承継」。多くの中小企業経営者が「まだ先のこと」と思いがちですが、理想的な承継には5年以上の準備期間が必要だといわれています。
特に日本では後継者不足が深刻化し、優良な企業でも後継者がいないために廃業を選ぶケースが増加しています。自分の会社を次世代に残したい、従業員の雇用を守りたいと考えるなら、今から事業承継について考え始めるべきでしょう。
しかし、どこから手をつければよいのか、どのような方法があるのか、誰に相談すべきなのか、多くの疑問が浮かぶはずです。
この記事では、事業承継の基本から実践的なステップ、活用すべき支援制度まで、経営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。これからの時代に合った事業承継の形を見つけ、長年培ってきた事業を円滑に次の世代へつなげるための道筋を示していきましょう。
事業承継とは?今なぜ注目されているのか
「事業継承」という言葉を目にして、この記事に訪れた方も多いのではないでしょうか。ここでは、近年事業継承が注目を集めている理由について詳しく見ていきます。
事業承継の定義と目的
事業承継とは、会社の経営者が自身の持つ経営権や資産、経営ノウハウなどを後継者に引き継ぎ、事業の存続と発展を図るプロセスです。単なる社長交代ではなく、会社の資産・負債、事業価値、顧客や取引先との関係、企業文化、従業員の雇用など、事業に関わるあらゆる要素を次世代へ承継する総合的な取り組みといえます。
事業承継の目的は、主に以下の3つに集約するでしょう。
- 事業の継続と発展:創業者や現経営者が築き上げた事業を絶やさず、さらに発展させていくこと
- 雇用の維持:従業員の仕事と生活を守ること
- 地域経済への貢献:地域に根ざした事業活動を通じて、地域経済の活力を維持すること
適切な事業承継は、経営者個人の引退計画であると同時に、会社の未来を左右する重要な経営戦略でもあります。計画的に進めることで、円滑な世代交代と事業の持続的成長を実現できます。
中小企業を取り巻く現状と課題
日本の中小企業は今、深刻な事業承継問題に直面しています。中小企業庁の調査によれば、2025年までに70歳を超える中小企業経営者は約245万人で、そのうち約半数が後継者未定とされています。
この「2025年問題」に対応できなければ、約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるのです。
事業承継を困難にしている主な要因は以下の通りです。
- 経営者の高齢化:平均引退年齢は70歳超と年々上昇
- 後継者不足:子どもが事業を継ぎたがらない、適任者がいない
- 事業承継の準備不足:計画的な準備を行っている企業は約30%にとどまる
- 相続税や贈与税の負担:自社株式の評価額が高くなると税負担が重くなる
これらの課題に対応するため、政府は事業承継税制の特例措置や補助金制度の拡充など、支援策を強化しています。しかし最も重要なのは、経営者自身が早期に事業承継を意識し、計画的に準備を進めることでしょう。
事業承継で引き継ぐべき3つの資源
次に、事業継承で引き継ぐべき3つの資源についてみていきましょう。
- 人
- モノ
- コト
それぞれ分けて詳しく解説します。
人:経営権・後継者の育成
事業承継において最も重要なのが「人」の承継、つまり経営権の移転と後継者の育成です。経営権の承継は、法的には代表取締役の交代や株式の移転によって行われますが、実質的な経営権の移行はそれだけでは完結しません。
後継者育成のポイントは、以下の通りです。
- 早期からの計画的な育成:最低でも3〜5年の育成期間が必要
- 段階的な権限委譲:決裁権限や担当部門を徐々に任せていく
- 社内外での経験蓄積:様々な部署での経験や外部での修行も有効
- ステークホルダーとの関係構築:取引先や金融機関、従業員との信頼関係づくり
- 経営者としての意識付け:経営者目線での判断力や決断力の養成
実際の承継では、現経営者が一線から退くタイミングや後継者のサポート体制の構築も重要です。完全に引退するのではなく、会長職などで一定期間サポートする形が円滑な承継につながるケースも多いでしょう。
モノ:資産・株式・設備の承継
「モノ」の承継とは、会社の有形・無形の資産を後継者に引き継ぐことを指します。具体的には、自社株式、事業用資産(不動産、設備など)、資金(預金、借入金など)が対象となります。
特に重要なのが自社株式の承継です。経営権を確保するためには、通常、発行済株式の過半数を後継者が保有する必要があります。株式の移転方法としては、贈与、相続、売買などがありますが、それぞれ税務上の取り扱いが異なるため、慎重な検討が必要です。
株式承継における主な検討ポイントは以下の通りです。
- 株式の評価額:非上場株式の場合、複雑な評価方法によって決定
- 相続税・贈与税の負担:高額な税負担が生じる可能性がある
- 株式分散の防止:相続によって株式が分散しないための対策
- 資金調達:株式取得のための資金をどう準備するか
これらの問題に対応するためには、税理士や弁護士などの専門家の助言を得ながら、計画的に進めることが不可欠です。また、事業承継税制や各種の資金調達手段を活用することも検討しましょう。
コト:経営理念やノウハウの継承
「コト」の承継は、目に見えない経営資源を引き継ぐことです。具体的には、経営理念、企業文化、経営ノウハウ、取引先との関係、従業員との信頼関係などが含まれます。これらは文書化されていないことも多く、承継が難しい要素です。
経営ノウハウの継承ポイントは以下の通りです。
- 「暗黙知」の「形式知」化:経営者の頭の中にある知識やノウハウを可視化
- マニュアルや業務フロー図の作成:業務プロセスの標準化と文書化
- メンター制度の活用:現経営者が後継者をOJTで指導
- 定期的な対話の場の設定:経営判断の背景や考え方を伝える機会を作る
- 顧客・取引先への共同訪問:人間関係や交渉術を実地で学ぶ
「コト」の承継は時間がかかるため、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。また、すべてを踏襲するのではなく、時代に合わせて変革すべき点は変革する柔軟性も重要でしょう。
事業承継の主な3つの方法
次に、事業継承の主な3つの方法を見ていきます。
- 親族内承継
- 社内承継
- M&A
それぞれ詳しく解説します。
親族内承継
親族内承継は、経営者の子や配偶者、兄弟姉妹などの親族に事業を引き継ぐ方法です。従来は最も一般的な承継方法でしたが、近年では子どもが事業を継がないケースも増えています。
親族内継承のメリット・デメリットは以下の通りです。
- 創業家の理念や価値観を継続しやすい
- 幼少期から事業への理解を深められる
- 取引先や従業員に安心感を与えやすい
- 親族内での調整が比較的行いやすい
親族内承継を成功させるためには、後継者の適性を冷静に見極め、十分な育成期間を設け、株式の集中と分散防止策を講じることが重要です。また、相続税や贈与税の負担を軽減するため、特例事業承継税制などの制度を活用することも検討すべきでしょう。
社内承継
社内承継は、従業員や役員など社内の人材に事業を引き継ぐ方法です。近年、親族内に適任者がいない経営者が増えたことで、この方法を選択するケースが増えています。
社内承継の主な特徴は以下の通りです。
- 事業への理解度が高い:社内の事情や業界知識を持っている
- 従業員からの信頼・支持を得やすい:人間関係がすでに構築されている
- 取引先や顧客との関係維持が容易:すでに面識があることが多い
- 企業文化や経営理念の継続性が高い:社内で育ってきた人材のため
ただし、最大の課題は株式取得資金の問題です。経営権を確保するための株式を購入する資金を、従業員個人が用意することは容易ではありません。この問題に対処するためには、以下のような方法が考えられます。
- 分割払いによる株式譲渡:長期間にわたって分割で支払う
- 会社による自社株買い:会社資金で株式を買い取り、後継者に譲渡
- 種類株式の活用:議決権と配当受領権を分離する
- MBO(マネジメント・バイアウト):金融機関からの借入を活用
社内承継を成功させるためには、後継者候補の早期選定と計画的な育成、株式取得のための資金計画、経営陣や従業員の理解と協力が不可欠です。
M&A
M&Aによる第三者承継は、社外の企業や個人に事業を売却する方法です。後継者不在の場合の選択肢として、近年急速に増えています。
M&Aの主なメリット・デメリットは以下の通りです。
- 適切な買い手を選べば事業の存続が可能
- 雇用条件維持を交渉条件にできる
- 株式売却によるまとまった資金の獲得
- 買い手企業とのシナジーによる成長機会
また、M&Aを進める一般的なステップは以下の通りであり、少し複雑な手順を踏む必要があります。
- 自社の現状把握と企業価値評価
- M&A仲介会社や金融機関への相談
- 買い手候補の選定とアプローチ
- 基本合意書(LOI)の締結
- デューデリジェンス(資産査定)
- 最終契約の締結と株式譲渡
- PMI(買収後の統合)
M&Aを成功させるためには、専門家の支援を受けながら、慎重に進めることが重要です。特に、会社の価値を適正に評価し、従業員の雇用条件や取引先との関係維持について明確な合意を得ることが必要です。
事業承継の基本ステップ
続いて、事業継承の基本的なステップを確認していきましょう。
- STEP1:現状把握と課題整理
- STEP2:後継者候補の選定と育成
- STEP3:事業承継計画の策定と実行
それぞれ詳しく見ていきます。
STEP1:現状把握と課題整理
事業承継の第一歩は、自社の現状を客観的に把握し、課題を整理することです。この段階で明確にすべき主な項目は以下の通りです。
| 事業面の現状把握 | • 売上高、利益率、キャッシュフロー等の分析 • 業界動向、自社の強み・弱み、成長性 • 特定の取引先や人材への依存度、潜在的なリスク要因 |
| 資産・負債の現状把握 | • 資産・負債の実態把握 • 株式の保有状況、評価額の試算 • 経営者個人の負担状況 |
| 人的資源の現状把握 | • 年齢構成、キーパーソンの特定 • 親族内、社内、社外の候補者リストアップ • 権限委譲の状況、意思決定プロセス |
この現状把握に基づき、事業承継にあたっての課題を明確化します。課題の例としては、「株式の集中と分散防止」「後継者育成」「借入金や個人保証の解消」「収益力の強化」などが挙げられるでしょう。
課題整理のためには、「事業承継診断」や「事業承継計画書」の作成が有効です。商工会議所や支援機関、専門家の協力を得ながら、体系的に進めることをおすすめします。
STEP2:後継者候補の選定と育成
後継者の選定と育成は、事業承継の成否を左右する最も重要なステップです。理想的には、承継の5〜10年前から計画的に進めることが望ましいでしょう。
後継者選定の基準として、以下の指標を考えてみましょう。
- 経営者としての資質:リーダーシップ、決断力、ビジョン構築力
- 業界や事業への理解:専門知識、経験、人脈
- ステークホルダーからの信頼:従業員、取引先、金融機関からの支持
- 熱意と覚悟:経営者としての責任を全うする意志
後継者が決まったら、段階的な育成プログラムを実施します。具体的な育成ステップの例は以下の通りです。
| 基礎的な業務経験(1〜2年目) | • 現場での実務経験を積む • 社内の各部門を経験する • 業界や市場への理解を深める |
| マネジメント経験(3〜4年目) | • 部門責任者としての経験 • 予算管理や人事管理を任せる • 新規プロジェクトのリーダーを務める |
| 経営参画(5年目以降) | • 経営会議への参加 • 経営計画の策定への関与 • 取引先や金融機関との関係構築 |
育成過程では、定期的な評価と振り返りを行い、必要に応じて計画を修正することが重要です。また、外部のセミナーや研修、他社での修行なども効果的です。
現経営者は「教え過ぎない」「失敗させて学ばせる」「徐々に権限を委譲する」などの姿勢を持ち、後継者の主体性を尊重することが成功の鍵となります。
STEP3:事業承継計画の策定と実行
事業承継計画(サクセッションプラン)は、承継の道筋を明確にするロードマップです。後継者が決まったら、具体的なスケジュールと行動計画を策定します。
事業承継計画に盛り込むべき要素は以下の通りです。
- 承継の全体スケジュール(タイムライン)
- 株式・財産の承継方法と時期
- 後継者の育成計画と評価基準
- 経営権の移行スケジュール
- 税務・法務上の対策
- リスク要因と対応策
計画策定後は、以下のようなステップで実行に移します。
| 1.株式・財産の承継準備 | • 株式評価の確定 • 株式移転の方法決定(贈与、売買等) • 資金計画の策定 • 必要な特例措置の申請準備 |
| 2.経営権の段階的移行 | • 重要意思決定への後継者の参画 • 役員や従業員への説明 • 取引先・金融機関への紹介 • 代表権の移行 |
| 3.承継後のサポート体制構築 | • 現経営者の関与度合いの設定 • アドバイザー役の設定 • 定期的な経営会議の開催 • 後継者の自主性を尊重する環境作り |
計画の進捗は定期的に確認し、環境変化に応じて柔軟に修正することが重要です。また、親族内承継、社内承継、M&Aなど、承継方法によって具体的なアクションプランは異なるため、選択した方法に適した計画を立てることが必要です。
事業承継で活用すべき支援制度
事業承継で活用できる支援制度はいくつか存在します。
税制特例措置と補助金制度
事業承継を支援するため、様々な税制特例措置や補助金制度が用意されています。これらを活用することで、承継に伴う税負担の軽減や必要な資金の調達が可能になります。
| 制度名 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事業承継税制 (特例措置) | 非上場株式等に係る贈与税 ・相続税の納税猶予 ・免除制度 | 令和9年3月31日までの 特例措置として、 発行済株式総数の 最大100%まで対象 |
| 個人版事業承継税制 | 個人事業者の事業用資産に係る贈与税 ・相続税の納税猶予 ・免除制度 | 土地、建物、 機械・器具備品等が対象 |
| 中小企業 経営承継円滑化法 | 金融支援(信用保証、制度融資等) | 事業承継に必要な資金調達を支援 |
また、助成金には以下のようなものがあります。
| 制度名 | 概要 | 補助上限・補助率 |
|---|---|---|
| 事業承継・引継ぎ 補助金 | 事業承継・M&Aに伴う専門家活用費用等を補助 | 最大600万円・補助率2/3 |
| 後継者育成支援事業 | 後継者育成に必要な研修等の費用を補助 | 都道府県により異なる |
| 経営承継 円滑化支援事業 | 事業承継計画策定や専門家派遣等の支援 | 一部無料、 一部自己負担あり |
これらの制度を利用するには、事前の計画策定や申請手続きが必要です。特に事業承継税制の特例措置は期限があるため、早めの対応が重要です。制度の詳細は、中小企業庁のウェブサイトや最寄りの商工会議所、支援機関で確認しましょう。
なお、これらの支援制度は頻繁に改正されるため、最新情報を専門家に確認することをおすすめします。
専門家や支援機関の活用法
事業承継は専門的な知識が求められる複雑なプロセスです。円滑に進めるためには、専門家や支援機関の力を借りることが不可欠です。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 株式評価、税務対策、節税策の提案 |
| 弁護士 | 契約書作成、株主間協定、トラブル対応 |
| 公認会計士 | 財務分析、企業価値評価、デューデリジェンス |
| 中小企業診断士 | 事業計画策定、経営改善、後継者育成 |
| M&A仲介機関 | 買い手探し、M&A全体プロセスの支援 |
また、主な支援機関としては以下があります。
- 事業承継・引継ぎ支援センター:各都道府県に設置、無料相談や専門家派遣
- 商工会議所・商工会:初期相談、セミナー開催、専門家紹介
- 金融機関:資金調達支援、M&Aマッチング
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構:各種支援ツールの提供、専門家派遣
特に初期段階では、無料相談を実施している公的支援機関の利用がおすすめです。ある程度方向性が固まったら、専門分野ごとに適切な専門家を選定し、チームとして協力を得ることで、効率的かつ効果的な事業承継を実現できるでしょう。
まとめ:円滑な事業承継のために今すべきこと
事業承継は、経営者にとって避けて通れない重要な経営課題です。円滑な承継には長期的な視点と計画的な準備が不可欠です。本記事の内容も参考に自社に最適な事業継承の形を探してみてはいかがでしょうか。