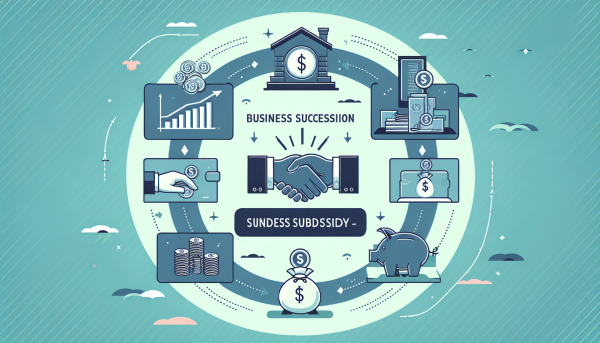「創業者の社長が亡くなった。会社の株式は、誰が相続するのだろう?」
「後継者は、経営手腕に優れている人なのだろうか?」
代表取締役として会社を経営していた親族が亡くなった場合、故人が保有していた会社の株式を相続人のうち誰が相続するのか、という相続財産の配分の問題が生じます。また、故人が経営を担ってきた会社の経営権を誰が承継するのかという問題もあります。
相続財産の適切な分割・配分に加え、経営権のスムーズな移行が求められます。これらが円滑に進まない場合には、無用なトラブルとなるばかりか、企業の成長にも支障を来します。
この記事では、会社の相続に関する重要事項全般について、分かりやすく、丁寧に解説しています。最後まで読むと、会社の相続の方法や各種の手続きに関する理解が深まり、スムーズな経営権の承継が可能になるでしょう。
会社相続の仕組みと重要性
会社は、法人格を有し、自然人とは独立した権利義務の帰属主体です。このため、会社の経営者が亡くなったとしても、会社財産が会社経営者(被相続人)の相続財産となることはありません。
会社の相続と事業承継の違い
会社の相続は、会社経営者が亡くなった場合に、相続人が株式について所定の手続きを経て引き継ぐことをいいます。他方、事業承継は、会社の経営権や資産を、現在の経営者から次世代に引き継ぐプロセスをいい、必ずしも現在の経営者に相続が開始したか否かを問いません。
会社の形態によって異なる相続の進め方
被相続人によって遂行されてきた事業が法人としての事業形態で行われてきたのか、それとも個人事業としての形態で行われてきたか、を見極める必要があります。
個人事業の相続と遺産分割
個人事業(自営業)の場合には、事業用資産と個人用(家庭用)資産とが混在していることが少なくありません。このような場合には、その財産が相続財産を構成する個人用(家庭用)財産なのか、それとも事業用資産なのかを判別することが重要です。
被相続人による遺言(公正証書遺言等)や相続人間でなされた遺産分割協議等の結果、当該個人事業を承継する相続人が事業用資産を引き継ぐことになれば、手続きはスムーズに進みます。
もっとも、遺産分割においては、相続財産の多くが事業用資産を構成する場合には、他の相続人の了解を得にくくなり、相続手続きがなかなか進まないおそれも生じます。
このような場合には、弁護士や税理士等の専門家を起用して、第三者による客観的な見地から事業用資産と個人用(家庭用)資産の区別を行うと良いでしょう。
法人の相続と株式の承継
被相続人による事業が会社形態で行われている場合、後継者は、会社の株式のうち、少なくとも50%超を保有することが必要です(会社の定款変更等を行う場合には、50%超では足りず、3分の2以上の株式を保有しておく必要があります)。
このため、相続人のうち、会社の事業を承継する者は、遺産分割協議において当該会社の株式のうち(少なくとも)過半数の保有を最優先するべきです。
経営権の引き継ぎと株主総会の重要性
会社の代表取締役として経営権を得るには、会社が(臨時)株主総会を招集し、事業を承継する相続人を取締役に選任するとともに、その後の取締役会において代表取締役に選任される必要があります。
会社の登記変更と手続き
会社の機関決定手続きの後は、役員変更に関する登記手続きを行う必要があります。登記の専門家である司法書士に手続きを依頼することにより、後継者や従業員の稼働を削減することができます。
会社の相続手続きと必要な流れ
会社の相続に関する諸手続きに関して、特に留意すべき項目を整理しておきます。
株式の状況把握と名義変更
後継者は、相続時点におけるその会社の株式の状況をしっかりと把握しておかなければなりません。被相続人が単独で100%の株式を保有していた場合には、遺産分割でも後継者となる相続人がその株式を100%相続することになるよう、相続人間で調整しておきます。
加えて、後継者による株式保有について、株主名簿の名義変更(名義書換)を行うことも忘れてはなりません。
株式の評価額の算定方法
株式の相続においては、その価値評価が重要です。株式の評価方法は、上場企業の株式と非上場企業の株式とで異なります。
上場企業の株式評価
上場企業の株式評価は、「被相続人が亡くなった日の終値」「被相続人が亡くなった月の平均株価」「被相続人が亡くなった前月の平均株価」「被相続人が亡くなった前々月の平均株価」のうち、最も低額のものを相続時の株価とします。
非上場企業の株式評価
非上場企業の株式は、上場企業の株式と異なり、その株式の市場価格というものがありません。このため、上場企業のうち、当該会社と類似する業種・企業の株価を参考にする等して株式評価を行います。
株式評価は、高度で専門的な知識を要するため、税理士や公認会計士の他、銀行・証券会社等の金融機関に相談すると良いでしょう。
経営権の確保と後継者の選定
既述のように後継者が安定的な会社経営を行うためには、少なくとも過半数、可能であれば3分の2以上の株式を保有する必要があります。
複数名の相続人による株式分散保有を避けるため、被相続人は生前から遺言を公正証書により残したり、生前贈与を活用することを通じ、将来における相続人間のトラブルの発生を防ぐことが重要です。
会社を相続する際に発生する税金と対策
相続人が相続税の納税にあたり、その資金を調達する必要が生じることがあります。後継者の資産状況が悪化した場合には、会社の信用力の低下をもたらすおそれにつながるため、特に注意する必要があります。
株式相続にかかる税金(相続税・贈与税)
まず、株式に係る相続税については、既述のとおり、上場株式については被相続人が亡くなった日の終値等のうち、最も低額な金額で評価を行います。
次に、贈与税については、次のように計算を行います。
実際の税額の計算等については、税理士や公認会計士等の専門家のアドバイスを受けると良いです。
事業承継税制の活用
事業承継税制は、後継者が事業を承継するために取得した株式に対する相続税・贈与税について、その納税の猶予や免税を受けることができる制度です。
所定の要件を充足すれば後継者の税負担が軽減されるため、事業を承継しやすくなります。事業承継税制には、一般措置と特別措置の2種類があります。
非上場株式の納税猶予・免除制度
非上場株式についても、一定の納税猶予や免除を受けることができる制度があります(「法人版事業承継税制」)。
後継者は、その非上場株式等に係る相続税について、一定の要件を充足すれば、納税が猶予され、後継者の死亡等により、猶予された相続税の納付が免除されます。
適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等を受ける必要があり、各都道府県に照会する必要があります。
株式の評価額を下げる方法
後継者としては、相続に伴う納税が過度に負担となる場合、承継した会社経営に支障を来すおそれがあります。こうした事態を回避するため、税負担の軽減を目的として、株式の評価額を下げることが行われます。
以下は、いずれも会社の純資産額を減らすことに着目した手法です。
- 先代経営者に対して退職金を支給する
- 遊休資産や含み損のある資産を売却する
- 投資不動産を購入する
会社相続で発生する可能性のあるトラブルと対策
会社相続には、トラブルが発生しがちです。ここでは、主要なトラブルの概要とその対応策を説明します。
兄弟間のトラブルを避けるには
兄弟の相続人間で生じるトラブルの典型は、相続財産の帰属の他、「誰が経営権を握るか」です。被相続人が保有していた株式を後継者に集中的に配分しようとすると、他の相続人が不満を持ち、遺産分割協議が整わないことがあるのです。
対応法としては、後継者以外の相続人に配慮し、会社の株式以外の相続財産を後継者以外の相続人に優先配分することにより、不満が出ないようにすることが考えられます。
また、被相続人においても生前から相続人間でトラブルが生じないように、遺言(公正証書遺言)や生前贈与を行うことを通じ、前もって後継者をハッキリとさせておくことも肝要です。
会社の負債を相続するリスク
経営者は、銀行等より会社の事業資金の融資を受ける際、経営者自身を保証人とすることが少なくありません。経営者に相続が発生した場合には、相続人は保証人としてのリスクに直面する場合があります。
また、銀行等が後継者に対し、保証人としての立場を引き継ぐよう、求める場合もあります。さらに、会社が抱える負債の有無や返済能力にも注意を払う必要があります。
経営権の掌握ができないケース
事案によっては、後継者に株式を集中できない場合もあり得ます。その場合、後継者と他の株主との間で株主間契約を締結し、特段の事情のない限り、後継者の経営方針に賛成する旨の条項を定めることが考えられます。
ただし、株主間契約については、他の相続人に拒否権を与えることにつながり、締結には慎重を期する必要があります。株主間契約の締結を必要とする場合には、企業法務に精通した弁護士に相談してください。
遺留分と相続人間の対立
相続手続きでは、遺留分への配慮が欠かせません。遺留分とは、相続人の一部(兄弟姉妹を除く相続人)が一定の割合で遺産に対する権利を有し、それが侵害される場合には、その侵害に応じた範囲で、遺言等の効力を否定することができる権利です。
遺留分が侵害されている場合には、相続人から遺留分減殺請求権が行使されることにより遺言等の効力が否定されることになります。
遺言等で株式の相続を後継者に集中させる際は、他の相続人の遺留分を十分に考慮したうえで行うことが必要になります。
会社相続における生前対策
会社の相続を円滑に行うためには、被相続人が存命中に対策を講じておくことが効果的です。
遺言書の作成
被相続人が生前に遺言を作成し、後継者や株式の取扱い等について、自らの意思を示しておくと良いでしょう。もっとも、遺言について民法は厳格な要式性を求めており、法定されている事項以外は、たとえ遺言の中に定めたとしても、法律上の効力を有しないのです。
遺言を作成する際には、自筆証書遺言とすることもあり得ますが、公正証書遺言がおススメです。公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、法律専門家である公証人が作成に関与するため、遺言の要式性を担保できるだけでなく、内容の不明確性を避けることもできるからです。さらに、原本は公証役場で保管されるので、偽造等の心配もありません。
生前贈与での株式移転
被相続人からの生前贈与により株式を後継者に移転させる方法です。これにより、確実に後継者に経営権を取得させることができます。
ただし、生前贈与を行う際には、他の相続人の遺留分を侵害することがないよう、必要に応じ、相続に詳しい法律事務所・弁護士に相談すると良いでしょう。
家族信託の活用
家族信託とは、信頼できる親族に自らの財産の管理・運用を委ねる仕組みをいいます。これにより、現在の会社経営者が自らの意思に従い、会社の株式を後継者(受託者)に取得・保有させ、後継者は受託者として現在の会社経営者のために株式を管理し、亡くなった後は、後継者自身を帰属権利者として設定します。
家族信託の個別設定は、金融機関に提案を依頼すると良いでしょう。
事業承継税制の活用
事業承継税制は、事業承継のために相続・贈与した財産の相続税・贈与税を猶予・免除する制度です。これを利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
後継者には一定割合以上の株式保有の他、実際の経営への関与等も必要になり、これを欠く場合には、税制の適用を受けられなくなることがあります。
M&Aによる会社売却の選択肢
後継者を探したものの、適任者が見つからないという事案もあります。そのような場合には、会社を親族や従業員以外の第三者に売却するM&Aという手法も検討対象といえます。次章で解説を加えます。
会社を相続したくない場合の選択肢
相続人の中には、被相続人の経営者としての苦労等を間近で見て、経営者としての地位を承継する意思を持つことができないという場合もあります。その場合、相続人が相続を放棄するという選択をすることがあります。
相続放棄の基礎知識
さらに、上記に加え、相続人が相続財産調査を行ったところ、会社の株式の他に目立った財産を見つけることができなかったり、被相続人が生前、多額の返済困難な負債を抱えていた等の事実が判明した場合にも、相続人は相続放棄をすることがあります。
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄は、時間的な制約があり、相続開始を知った時から3ヵ月以内に行う必要があります。このため、相続人は、速やかに相続財産調査を行い、法定相続分に従って相続するか、相続放棄するか等を判断する必要があります。
M&Aで会社を売却するという選択肢
相続人が相続を放棄したり、現在の経営者がビジネスから引退することを決意し、親族や従業員の中に後継者として適任者を見つけることができない場合等には、会社を第三者に売却する(M&A)ことも考えられます。
専門的知識を豊富に持つM&A仲介業者が最適の事案を提案することができますので、こうした専門家に提案を依頼してみることも良いでしょう。
まとめ:会社の相続を適切に行う際の重要なポイント
会社の相続は、会社株式の相続財産としての配分の問題にとどまらず、会社の持続的な成長を進めるうえで極めて重要な事項です。相続発生後における相続人間のトラブルの発生を避け、後継者に円滑に経営権を引き継がせ、企業として成長し続けるためには経営者の生前における準備も不可欠です。