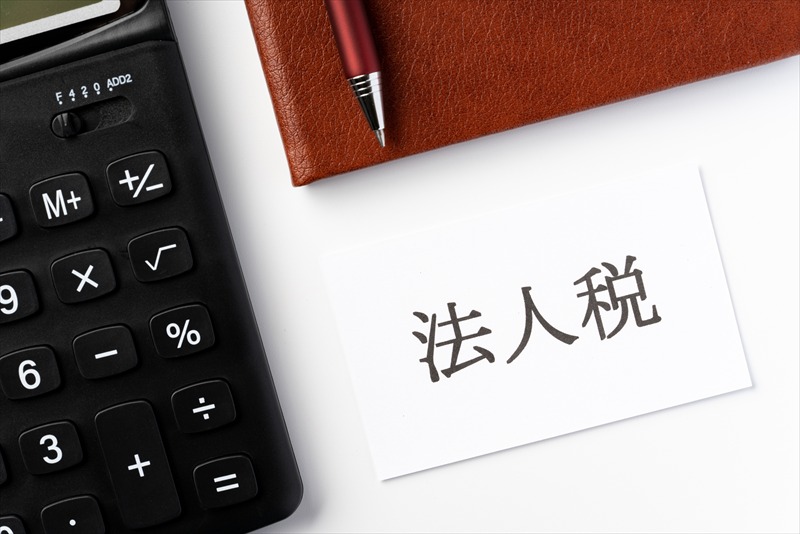
法人経営者なら誰もが直面する「法人税」の壁。
正しい知識がないまま税務申告をしていると、知らず知らずのうちに多額の追徴課税を課されるリスクを抱えているかもしれません。
「税理士に任せているから大丈夫」と思っていても、基本的な知識がなければ、経営判断のたびに頼りきりになり、迅速な意思決定ができなくなってしまいます。
この記事では、法人税の基礎から計算方法、申告手続き、そして効果的な節税対策まで、実務で即活用できる知識を提供しています。
法人税とは?
法人税とは、法人の事業活動で生じた利益に対して課される国税です。会社が稼いだお金から経費を引いた「もうけ」に対してかかる税金と考えるとわかりやすいでしょう。株式会社や合同会社など法人格を持つ組織が納税義務者となります。
法人税は国に納める税金ですが、これとは別に都道府県や市区町村に納める「法人住民税」「法人事業税」もあります。これらをまとめて「法人三税」と呼ぶこともあります。
個人の所得税との違い
法人税と所得税は課税対象と計算方法に大きな違いがあります。所得税は個人の所得に対して累進課税(所得が多いほど税率が上がる)が適用されますが、法人税は原則として一律の税率が適用されます。
所得税と法人税の主な違いは以下の通りです。
- 課税対象: 所得税は個人の所得、法人税は法人の所得に課税
- 税率構造: 所得税は5%〜45%の累進課税、法人税は資本金等により15%〜23.2%の税率
- 控除項目: 所得税には基礎控除や配偶者控除があるが、法人税にはない
- 損失繰越: 法人税は最大10年間の繰越控除が可能
法人税がかかる法人とかからない法人
すべての法人に法人税がかかるわけではありません。一般的な会社には法人税がかかりますが、公益法人などには特例があります。
| 法人税がかかる法人 | 株式会社、合同会社などの営利法人 一部の協同組合、医療法人など 一般社団法人 財団法人(収益事業を行う場合) |
| 法人税がかからない法人 | 国や地方公共団体 公益法人(収益事業を行わない場合) |
会社を設立したら、まず法人税の納税義務があると考えておきましょう。NPO法人や一般社団法人でも、収益事業を行えば法人税の申告が必要です。
法人税の計算方法と税率
法人税は「課税所得×税率」で計算します。ここで重要なのは「課税所得」の求め方です。会社の帳簿上の利益(税引前当期純利益)がそのまま課税所得になるわけではありません。
法人税の計算は大まかに次の流れになります。
- 会計上の利益(税引前当期純利益)を計算
- 税務上の調整(加算・減算)を行う
- 課税所得を確定させる
- 税率をかけて税額を計算
これに地方税(法人住民税・法人事業税)を加えると、実効税率は中小法人で約25〜30%、大法人で約30〜35%程度になります。
税引前当期純利益と課税所得の違い
会計上の「税引前当期純利益」と税務上の「課税所得」は同じではありません。税法には独自のルールがあり、会計上の数字を調整する必要があります。
- 交際費: 会社が支払った接待費などは、一部税務上認められない
- 減価償却: 会計上と税務上で計算方法が異なることがある
- 役員給与: 決まった要件を満たさないと経費として認められない
- 寄付金: 全額が経費になるわけではなく、一部しか認められないことがある
例えば、取引先との会食で10万円使った場合、会計上は全額経費になりますが、税務上は一部しか認められないことがあります。この差額分を「加算」して課税所得を計算します。
法人税率をざっくり理解する
法人税率は会社の規模によって異なります。初めての確定申告では、まずは自社がどの税率区分に入るかを確認しましょう。
- 中小法人(資本金1億円以下)
-
- 年800万円以下の所得:15%
- 年800万円超の所得:23.2%
- 大法人(資本金1億円超)
-
- 所得金額にかかわらず一律23.2%
ただし、2025年度(令和7年度)の税制改正により、中小法人に適用される軽減税率の特例が2年間延長されます。
その一方で、所得金額が年10億円を超える事業年度については、所得800万円以下の部分に適用される税率が15%から17%に引き上げられる見直しが行われます。
法人税の申告と納付方法
法人税の申告は事業年度終了後、2ヶ月以内に行う必要があります。3月決算なら5月末が期限です。申告が遅れると延滞税などのペナルティが発生するため、スケジュール管理が重要です。
初めての申告では準備に時間がかかるため、余裕をもって取り組みましょう。e-Tax(電子申告)を利用すると24時間申告できるので便利です。
特に初めて法人税の申告を行う場合は、税務署の相談窓口や税理士のサポートを活用することをお勧めします。
法人税の確定申告期限と申告方法
法人税の確定申告は、事業年度終了日から2ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
申告方法は主に2つあります。
- e-Tax(電子申告): インターネットで24時間申告可能、添付書類も電子データで提出
- 書面提出: 申告書を印刷して税務署窓口または郵送で提出
最近はe-Taxが推奨されており、書面申告よりも提出期限が伸びるなどのメリットがあります。e-Taxを利用するには電子証明書などの準備が必要ですが、一度設定すれば次回からはスムーズです。
法人の場合、以下3種類の書類を作成する必要があります。
- 別表一: 課税所得金額と法人税額の計算
- 別表四: 所得の金額の計算(税務調整)
- 別表五: 利益積立金額等の計算
初めての申告では税理士のサポートを受けることをおすすめします。
法人税の納付方法
法人税の納付方法は複数あり、自社に合った方法を選べます。納付期限も申告期限と同じく、事業年度終了後2ヶ月以内です。
- 金融機関窓口: 納付書を持参して窓口で納付
- ネットバンキング: インターネットバンキングから納付
- ダイレクト納付: e-Taxと連動して口座から自動引落
- クレジットカード納付: クレジットカードでの納付(手数料あり)
納付後は領収証書や納付受付通知などを保管しておきましょう。これらは税務調査の際などに必要になることがあります。
特に初めての納付では、納付手続きに慣れていないため、期限に余裕をもって準備することが大切です。計画的に資金を準備し、期限内に納付する習慣をつけましょう。
納付書の書き方と注意点
銀行窓口などで納付する場合、納付書の正確な記入が必要です。記入ミスがあると納付が正しく処理されないことがあります。
納付書を記入する際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 所轄税務署名: 自社の管轄税務署を正確に記入
- 法人名・所在地: 登記上の正式名称と所在地
- 法人番号: 13桁の法人番号
- 事業年度: 該当する事業年度
- 税目・税額: 「法人税」と納める金額
納付書は3枚綴りになっていることが多く、1枚目は税務署提出用、2枚目は領収証書、3枚目は控えとなります。納付後は必ず領収証書を保管しましょう。
納付書は税務署で入手できるほか、国税庁ホームページからダウンロードすることも可能です。
法人税を抑えるための節税対策
法人税を合法的に抑える「節税」は経営戦略の1つです。ただし、無理な節税は税務調査のリスクを高めるため、適切な範囲で行うことが重要です。
効果的な節税対策には以下のようなものがあります。
- 経費を適切に計上する
- 役員報酬の最適化
- 減価償却の活用
- 福利厚生の充実
- 各種税額控除の利用
節税は「脱税」とは全く異なります。税法の範囲内で税負担を軽減することが節税であり、違法な行為は厳しいペナルティの対象となります。無理のない範囲で実施することが重要です。
ここでは、3つの節税対策について詳しく解説します。
福利厚生を充実させる
福利厚生の充実は従業員の満足度向上だけでなく、法人税の節税にも効果的です。適切な福利厚生費は全額経費として認められます。
- 社会保険料の会社負担分: 全額経費計上可能
- 健康診断費用: 従業員の健康管理として全額経費に
- 社員旅行: 社内行事として認められれば経費に
- 社宅・住宅手当: 適正価格であれば経費計上可能
福利厚生制度を設計する際は、税務メリットと従業員満足度のバランスを考慮しましょう。
役員報酬を増額する
役員報酬の適切な設定は、会社と個人の税負担を最適化する重要な戦略です。役員報酬は経費(損金)として認められるため、会社の税負担を減らす効果があります。
- 定期同額給与: 毎月同額の報酬は原則として経費に計上可能
- 変更のタイミング: 原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定
- 適正水準: 会社の規模や業績に見合った金額であること
中小企業では、法人と個人の税金を合わせた「トータル税負担」の視点で最適な報酬水準を考えることが重要です。
毎年の決算状況を踏まえて適切な報酬設定を行いましょう。特に中小企業では、法人の利益と役員個人の所得税を合わせた「トータル税負担」の視点から最適な報酬水準を検討することが重要です。
法人税シミュレーションで節税対策を試す
効果的な節税計画には、様々な選択肢の効果をシミュレーションすることが重要です。エクセルなどを使って、異なる節税策のメリットを比較検討しましょう。
例えば、「設備投資を今年度に行うか来年度に延期するか」といった判断も、税負担シミュレーションがあれば合理的な意思決定ができます。シミュレーション結果を基に税理士と相談することで、より実践的な節税プランを策定できます。
シミュレーションツールは市販されているほか、税理士事務所が提供しているケースもあります。自社の状況に合った使いやすいツールを選びましょう。また、シミュレーション結果をもとに税理士と相談することで、より実践的な節税プランを策定できます。
法人税の計算・申告を効率化する方法
法人税の計算・申告業務は、効率化によって大幅に時間とコストを削減できます。特に中小企業では、限られたリソースを有効活用するために業務効率化が重要です。
申告を効率化する方法として、以下のようなものがあります。
- 会計ソフトを活用して計算を自動化
- 法人税申告業務を効率化するワークフローを構築する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
会計ソフトを活用して計算を自動化
会計ソフトの活用は、法人税計算の効率化と正確性向上に大きく役立ちます。特にクラウド型の会計ソフトは使いやすく、中小企業に適しています。
会計ソフトを活用するメリットは、以下の通りです。
- 自動仕訳: 銀行口座と連携して取引を自動で記録
- リアルタイム把握: 現在の財務状況をいつでも確認可能
- 申告書類作成: 決算データから申告書を自動作成
- データ共有: 税理士との情報共有がスムーズ
会計freee、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計など様々な商品がありますが、自社の規模や業種に合ったものを選択するのが重要です。
法人税申告業務を効率化するワークフローを構築する
法人税申告を効率的に進めるには、日常の経理処理から申告書提出までの一連の流れ(ワークフロー)を整備することが大切です。
以下のようなフローを意識することで、節税効果を最大化できるでしょう。
- 日次: 領収書のスキャンとクラウド保存、仕訳入力
- 月次: 月末の締め処理、試算表の確認
- 四半期: 税金の予測計算、資金繰り確認
- 決算前: 税務調整項目の洗い出し、節税対策の検討
- 決算: 決算整理仕訳の入力、申告書の作成
- 申告: e-Taxでの申告、納付手続き
特に小規模企業では1人で複数の業務を担当することも多いため、効率的な進め方が重要です。また、申告業務のスケジュールを年間カレンダーにまとめておくと、繁忙期の見通しが立てやすくなります。
税務書類は一度作成すれば翌年も同じフォーマットで作成できることが多いので、初年度はしっかりと手順を記録しておくとよいでしょう。
さらに、税務調査への備えとして、根拠資料の整理・保管方法も標準化しておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では、法人税の基礎から計算方法、申告手続き、節税対策まで幅広く解説しました。
税務知識は経営判断に直結する重要な要素です。税理士に丸投げするのではなく、基本的な仕組みを理解して主体的に関わることで、より効果的な経営判断ができるようになります。
また、税制は毎年のように変わるため、常に最新情報をチェックすることも忘れないようにしましょう。適切な税務知識を持つことで、企業経営の質と意思決定のスピードが向上するはずです。











