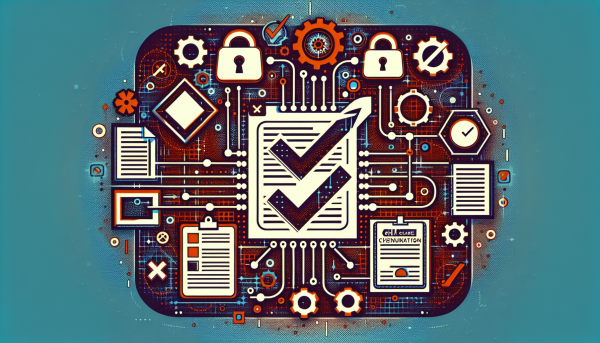M&Aを検討する経営者にとって、「どの手法を選ぶべきか」という判断は非常に重要です。なぜなら、どの手法を選択するかで、シナジー効果の創出や税金、対価の支払方法などが大きく変わるからです。
ですが、M&Aにはさまざまな種類やスキームがあり、それぞれの特徴やメリット・デメリットを正しく理解しなければ、最適な選択はできません。そこで本記事では、M&Aの代表的なスキームの特徴や選び方のポイントなどについて詳しく解説します。
M&Aにおける「スキーム」と「ストラクチャー」の違い
M&Aの現場では、「スキーム」や「ストラクチャー」という言葉が頻繁に使われます。そこでまず、それぞれの定義や特徴などについて解説します。
スキームとは?手法としての意味
M&Aにおける「スキーム」とは、取引全体の仕組みや枠組みのことです。たとえば「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」などがスキームに該当し、どの方法を使って企業を譲渡・統合するかという手法の違いを示しています。
こうしたスキームの選定は、売却目的、税務対策、法的要件、関係者への影響などを踏まえたうえで、専門家を交えて慎重に検討されます。なぜなら、目的に応じた適切なスキームの選択が、M&A成功の鍵を握っているためです。
ストラクチャーとは?法律的構造の意味
一方で「ストラクチャー」とは、選んだスキームをどのような法的・契約的構造で組み立てていくかという設計図のようなものです。
たとえば、株式譲渡スキームを選んだ場合でも、複数の出資者がいる場合の契約構成や持株比率の調整など、取引の具体的な設計を詰める作業がストラクチャー設計にあたります。
スキームとストラクチャーの関係性
スキームは「M&Aの全体の方向性」、ストラクチャーは「その実行方法」と捉えるとイメージしやすいでしょう。スキームで大枠を定めた後、それを実際に成立させるための具体的な設計がストラクチャーです。
たとえば、株式譲渡というスキームを採用しつつ、譲渡のタイミングや段階的な買収、役員構成の変更方法などをストラクチャーとして設計します。両者は切り離せない関係であり、セットで理解することが重要となります。
ただし、実際の現場では、スキームやストラクチャーは、ほとんどの同じ意味で用いられています。ですから、どちらも「M&Aの手法やその枠組み」と覚えておけば、問題ないでしょう。
M&Aで活用される主なスキームの種類
M&Aのスキームにはいくつもの種類があり、目的や規模、法的な状況によって、その選び方が変わります。そこで本章では、スキームごとの特徴について簡単に解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、売り手企業の株主が保有する株式を買い手企業に譲渡することで、会社の経営権を売り手から買い手へ移転させるスキームのことです。基本的に株主の構成が変わるだけであるため、法人格はそのままで、取引先や従業員との契約関係もそのまま引き継がれます。したがって、スムーズな事業継続が可能です。
また、登記や手続きが比較的簡単であることから、最も一般的な手法として、多くのM&Aで活用されています。ただし、負債や簿外債務もそのまま承継されてしまうため、買い手側にとっては事前のデューデリジェンスが非常に重要です。
また、売り手の税務や法務の状況によっては、買収リスクが高くなる場合もあるため、株式譲渡を選択する際には、慎重な判断が必要となります。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業のうち、一部門もしくは全部門の事業資産・負債や得意先との契約などを、選択的に売買するためのスキームです。譲渡対象を柔軟に設定できるため、赤字部門を除外するなど、売り手にとっては「売りたい部門だけを」、買い手にとっては「買いたい部門だけを」移転することが可能です。
また、債務も移転対象から外せるため、買い手にとってはリスクを限定しやすいというメリットがあります。一方で、従業員の雇用契約や取引先との契約などは、個別に契約し直さなければならないため、実務的な手間が非常にかかります。
さらに、税務上の扱いも複雑で、譲渡益課税や登録免許税、消費税などの費用も発生するため、全体のコスト計算とスケジュール管理は必須です。
合併(吸収合併・新設合併)
合併は、2つ以上の企業を1つに統合するスキームで、吸収合併と新設合併の2種類があります。
吸収合併では一方の会社が存続し、もう一方の資産・負債・契約などを包括的に引き継ぎます。これに対し新設合併では、既存の企業はすべて解散し、新たな法人を設立して資産などを承継します。
合併は、税務・会計・労務・法務すべての面で複雑な調整が必要であり、手続きにも時間がかかるのが難点です。ただし、明確な経営統合やブランドの一本化を図りたい場合には有効な手段となります。
会社分割(吸収分割・新設分割)
会社分割は、事業の一部を別の会社に分離するスキームです。吸収分割では、既存の会社から分離した事業を他社に承継させ、新設分割では、新しい会社を設立して事業を引き継がせます。
赤字部門の切り出しや、グループ内の組織再編などに使われることが多く、企業再編の柔軟な手段となります。ただし、事前準備や手続きが煩雑なことに加え、税務・会計上の配慮も必要となるため、専門家の関与が不可欠です。
株式交換・株式移転
株式交換は、買い手企業が買収対価として売り手企業の株主に自社株を交付することで、売り手企業を完全子会社化する手法です。これに対し、株式移転とは、売り手企業の株主が対価として持株会社の株式を取得し、企業グループの持株会社化を行うためのスキームです。
いずれも株式による支配権の取得を目的としており、現金を使わずに企業統合を実現できる点に特徴があります。どちらの手法も、主にグループ経営の再編やホールディングス体制への移行に活用され、スピード感のある統合が実現できますが、株価評価や支配権割合の調整には注意しなければなりません。
第三者割当増資
第三者割当増資は、買い手企業が売り手企業の新株を引き受けることで出資し、議決権を取得するM&A手法です。これにより買い手は売り手企業の株主となり、経営に影響を及ぼすことができます。
段階的な買収や少額出資にも適しており、提携強化や資本参加を目的としたM&Aで活用されます。ただし、持株比率によっては経営権を完全に掌握できない場合もあるため、出資目的や割合の調整が重要です。
スキームの選定で押さえるべきポイント
M&Aのスキームを選ぶ際には、買い手と売り手、それぞれの視点から適切に判断することが重要です。そこで本章では、スキームを選択する際に必要となるポイントについて解説します。
買い手企業の視点
買い手側がスキームを選定する際には、財務・税務の負担や統合後のシナジーを考慮しなければなりません。たとえば、株式譲渡は既存契約の継承が容易な一方で、負債も引き継ぐため、財務リスクへの備えが必要です。
また、事業譲渡であれば柔軟な引継ぎが可能ですが、手続きやコストが増える傾向にあります。どのスキームを選択するにしても、長所と短所があるため、統合後に得られる事業シナジーとのバランスを検討することが欠かせません。
売り手企業の視点
売り手側にとっては、M&Aによる事業承継のしやすさや、税務的なメリットもスキーム選定に大きな影響を与えます。たとえば、株式譲渡は会社全体を一括で売却できるため、スピーディーな事業承継が可能です。
また、一定の要件を満たせば、事業承継税制の適用により相続税の負担軽減が見込めます。ただし、従業員の処遇や取引先との関係など、譲渡後の影響にも十分配慮する必要があります。
スキーム選定で重要な判断基準
スキームを選ぶ際は、事業目的・財務状況・関係者への影響などを総合的に評価することが大切です。たとえば、短期的な売却益を重視する場合は株式譲渡、赤字事業の切り離しを優先するのであれば事業譲渡が適しています。
また、税務面の影響や手続きの負担、買収後の統合戦略(PMI)との整合性なども、重要な判断基準となります。
このように、スキーム選びの際には多面的な視点が必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら、自社の目的に合致した戦略的な意思決定を行わなければなりません。
M&Aスキームのメリット・デメリット比較表
M&Aには多様なスキームがあり、それぞれに異なる利点と注意点があります。ここでは主要な手法を整理し、比較できるよう一覧にまとめました。
| スキーム | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 経営権の移転がスムーズ。既存契約も引き継げるため、手続きが比較的簡単。 | 負債や簿外債務も引き継ぐリスクがある。 |
| 事業譲渡 | 売却対象を選べる。不要な資産・負債を除外できる。 | 契約や許認可の再取得が必要。手続きが煩雑。 |
| 合併 | 規模の拡大や効率化が図れる。企業ブランドの統合が可能。 | 統合の難易度が高く、従業員の混乱や文化の衝突も起こり得る。 |
| 会社分割 | 特定事業の切り出しや再編が可能。柔軟な再構築に向いている。 | 手続きが複雑で、関係者の理解と調整が必要。 |
| 株式交換・移転 | 完全子会社化によりグループ経営がしやすくなる。 | 親会社の株式発行により希薄化が起こる可能性がある。 |
| 第三者割当増資 | 資本提携を通じて関係強化や資金調達が可能。 | 既存株主の持株比率が低下し、支配権に影響が出る可能性がある。 |
M&Aストラクチャーを決定する際の注意点
M&Aのスキームやストラクチャーを決定する際は、税務・法務・統合後の経営体制など、さまざまな要素を踏まえた判断が必要です。ここでは、選定時に特に注意すべきポイントを整理します。
税務・会計・法務の影響
M&Aでは、選択したスキームによって、税金や会計処理が大きく変わります。たとえば、株式譲渡は譲渡益課税の対象となりますが、事業譲渡では、譲渡益課税だけでなく消費税の課税対象にもなります。
また、合併や会社分割は法的手続きが複雑なうえに、登記や公告の義務も果たさなければなりません。このように、どのスキームを選ぶかによって、法律で定められた手続きや税金などの処理方法が大きく変わるため、専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
統合プロセスの設計とスケジュール管理
統合のプロセスやタイムラインも、どのスキームを選ぶかによって異なります。たとえば、合併は複数の部門・人材・システムの統合が必要になるため、統合計画(PMI)とスケジュールの調整が不可欠です。
これに対し、株式譲渡は契約や資産・負債が包括的に譲渡されるため、手続きそのものにはそれほど時間はかかりませんが、従業員や取引先に対する丁寧な説明は必要です。
このように、スキームによって全体のスケジュールも大きく変わるため、こうした点も考慮しておかなければなりません。
よくある質問
最後に、M&Aのスキームやストラクチャーに関して、実務でよく寄せられる疑問や質問についてお答えします。
M&Aのスキームとストラクチャーの違いは?
スキームは「M&Aの手法そのもの(例:株式譲渡、事業譲渡など)」を指し、ストラクチャーは「その手法をどう実行するかという構造・設計」を意味します。スキームが戦術で、ストラクチャーは戦略と捉えると理解しやすいでしょう。
ただし、法律などで明確に区分されていませんし、実務上は、ほぼ同じ意味で使われています。
どのスキームが税務的に有利なのか?
税務上の有利・不利は、売り手・買い手の状況や目的によって異なります。たとえば、売り手にとっては株式譲渡が税務面で有利な場合が多いですが、買い手としては、のれんの償却が損金算入できる分だけ、事業譲渡の方が有利です。
このように、どのスキームが税務的に有利なのかは状況によって異なるため、専門家の助言を受けながら判断することをお勧めします。
中小企業のM&Aではどのスキームが主流?
中小企業のM&Aでは、手続きが比較的簡便な「株式譲渡」が主流です。特に、オーナー経営者による株式譲渡は、事業承継などの場面で、実際に数多く用いられています。
一方で、対象資産を選別したい場合には、事業譲渡も選ばれています。ただし、売却した対価は経営者個人ではなく会社に支払われるため、創業者利益の獲得や退職後の生活資金を目的とするようなケースでは、ほとんど選択されません。
まとめ
M&Aにおいては、目的や企業の状況に応じて最適なスキームやストラクチャーを選ぶことが重要です。ただし、それぞれの手法にはメリットとデメリットがあり、税務・法務・PMIなどへの影響も異なります。
したがって、スムーズなM&Aを実現するためには、専門家のサポートを活用しながら、自社に最も適した方法を見極める視点が欠かせないと言えるでしょう。